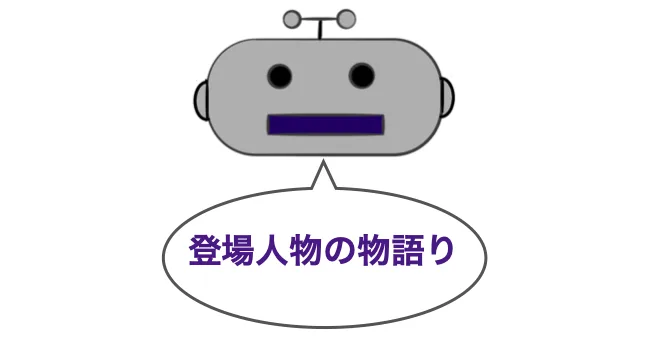日本文化– category –
-


サンタも鬼もゆるキャラも? 日本文化の“存在生成システム”を読み解く
サンタは実在するか?日本文化が示す「存在」の新しい視点 なぜ、サンタは実在しなければいけないの? 西洋のドラマで、サンタは実在するかしないのか、実在しないから信じない。というシーンを時々見かける。 その感覚に馴染めない、実在することと信じる... -


忍者ブーム再燃:欧米で忍者が再評価される理由とは?
Ninjaは世界でどう見られている?アメリカとヨーロッパの文化比較 “Ninja, Sushi, and Samurai”(忍者、寿司、侍)、 “Ninja, Zen, and Sushi”(忍者、禅、寿司) これらは欧米で日本文化を紹介するコンテンツでよく見られる表現だそうだ。 現代の海外の忍... -


「ものづくり」とは “つながり” である|人・自然・モノが紡ぐ日本文化の本質
日本の「ものづくり」とは?──単なる製造ではない “つながり” の哲学 日本の物作りは、合理性だけでは語りきれない。 「ものづくり」とは単なる製造ではなく、素材とのつながり、作り手と使い手の関係、さらには物を介した人々の絆を含めた深い概念である... -


桜が散る瞬間、なぜ心が動くのだろうか?
散りゆく桜に込められた想い―日本人が慈しむ儚さの真髄 自然の猛威はあらゆる物を破壊し、人の心に無常感を植え付ける。 負のイメージの強い無常感だが、日本の文化の中では様々に変化した。 移ろうことを愛で、儚さを慈しむ風習が生まれた。 日本は地震多... -

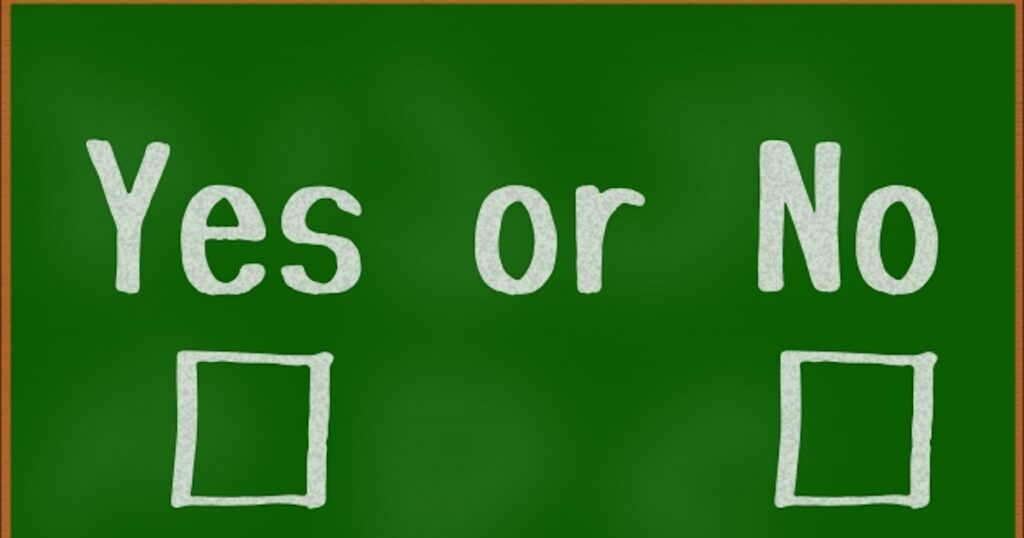
グレーゾーンが鍵!多様性を尊重する日本の価値観
曖昧さは弱さか?日本文化に隠された柔軟性の力を探る 西洋においては自己の確立が重要視され、自らの存在を明確にし、アイデンティティーを構築することが求められる。一方で、日本では個人の確立よりも関係性の中で自己を見出すことが重視され、自己を明... -


今この瞬間を愛でる:日本の四季と季節行事
「四季を愛でる心」―日本文化に根付く季節の楽しみ方 「日本には四季がある」と言うより、「四季を愛でる風習がある」。 過ぎ去る季節をただ眺めるのではなく、移ろい行く一瞬を丁寧に切り取る。それが四季を愛でる心だ。 「日本には四季がある」ってよく... -


日本文化におけるつながりと共存
日本の物作り×日本食:素材と人が紡ぐ共生の物語 日本食においては、食材の持つ本来の味や香り、食感を尊重することが重要である。過度な加工や味付けを避けることで、素材そのものの良さを引き出す。この姿勢は素材を「コントロール」するものではなく、... -


多様性が未来を変える!つながりが生む新たな価値とは?
日本文化における借景の美学 海外の人々にとって、日本の文化は自然と人間が一体化し、共存する姿として映るという。 庭園の前景に庭を配置し、遠方の山野と重ね合わせることで景観を構築する手法が借景である。これは、雄大な自然を庭の一部として取り込... -


日本文化の多様性とつながり|ゆるキャラと空気を読む文化を探る
日本文化の多様性 日本は太古の昔から、大陸の多様な文明を独自の形で発展させてきた。 島国である日本は、限られた価値あるもののみが海を越えて伝わってきたため、辿り着いた文物は捨てられることなく受け容れられ、後に吟味された。その結果日本は漂流... -


変化の文化日本
日本の再生文化 vs 西洋の永続文化|物への信頼とつながり 石の文化と木の文化についてのお話です ある旅番組を観ていた。 西洋を旅するその番組で、数百年の歳月を重ねた石組の遺跡を、そのまま住居として今も活用し続けている様子を紹介していた。 TVの...
12