日本の「ものづくり」とは?──単なる製造ではない “つながり” の哲学
日本の物作りは、合理性だけでは語りきれない。
「ものづくり」とは単なる製造ではなく、素材とのつながり、作り手と使い手の関係、さらには物を介した人々の絆を含めた深い概念である。
日本には、人と「モノ」のつながりを大切にする文化が根付いている。物を介して人と人がつながり、素材を通じて自然との一体感を得ることで、製品は単なる道具以上の意味を持つ。これは単なる製品の製造ではなく、見えない絆を丁寧に構築する行為である。
一方で、西洋のものづくりは合理性と効率性を重視する傾向にある。
製造者と消費者の関係は物と金銭の交換に基づいている。この交換は明確な目的に基づき、効率的に価値を提供することが中心となる。



日本の「ものづくり」って知ってますか?



日本と西洋で考え方が違うって聞いたことがあります



例えば大量生産されたプラスチックのコップがあります。これは効率的で安く作られて、壊れたらすぐに捨てて新しいものを買うことが多いんです



こわしたら、おわり?



日本の「ものづくり」では、人と「モノ」とのつながりをとても大切にしています
壊れた茶碗を金継ぎという技法で修理して、もっと美しく生まれ変わらせることもあるんです





日本では、作る過程も大切にされるんですよね?



素材や、作り手と使い手のつながりも大切にしているからです
たとえば、陶芸家が茶碗を作るとき、土の質感や使う人の手に馴染む感触まで考える。それによって、使い手はその茶碗を手に取るたびに作り手の心とつながることができるんです



物作りってただモノを作ることじゃないんですね



物作りは、単に目に見える物質を作るだけじゃなく、目に見えない人々の思いやつながりも含まれています
西洋では、作り手と使い手の関係は、お金でモノを交換することが中心なんですが、日本のものづくりでは、物を介した人々のつながりも含んでいます。作り手と使い手の心がつながることで、モノには特別な意味が宿るのです



モノ……つくる?おもい?



「思い」というのは、作り手の気持ちや誠意のことです
たとえば、日本の和包丁は、一つ一つ職人の手で丁寧に鍛え上げられます
その包丁が料理人の手に渡り、食材を通して人々に喜びを届ける。その思いが人と人とのつながりを生みます
また、料理人が道具を大切にすることで、人とモノとの絆も築かれるのです



つながり?きずな?



私たちがこうして話していることも、大切なつながりなんです
人と人、物と人のつながりが、私たちの世界を豊かにしていくんだよ



AIが発展している今、こうした心のつながりが見直されていますよね



AIは効率や合理性では人間以上の力を発揮することがあります
でも、「つながり」や「絆」の価値は、AIには模倣できない人間ならではのものなんです



だからこそ、モノを大切にする心が大切なんですね



その気持ちこそ、未来を豊かにする鍵なんです



ボンドも、つながりたい!おもい、だいじ!
「日本のものづくり」は、単なる物質的な製造ではなく、人間がモノにどのように向き合い、関係を築くかという哲学を含んでいる。
モノを通じて人と自然、人と物、人と人が深くつながることで、文化的な豊かさと心の深みを育んでいる。
現代社会ではAIの発展により、合理性がさらに重視される。しかし、合理性では人間がAIに勝ることは難しい。だからこそ、日本のものづくりが示す「つながり」や「絆」の価値は重要である。これは人間ならではの感性と共感から生まれる独自の価値であり、AIには模倣できない領域である。
自然を「師」とする日本のものづくり──四季と素材が育む技の精神
日本のものづくりは、自然との深い結びつきに基づいて発展してきたものである。
四季の変化が豊かな日本では、木工、漆器、陶磁器などが気候や素材の特性に応じて発展し、職人たちは自然を「師匠」として技術を磨いてきた。
また、「わび・さび」や柳宗悦の「用の美」思想により、不完全さや日常の道具の中に自然との調和を見出す美意識が育まれている。



日本のものづくりは自然と深く結びついて発展してきたんですよ



自然とものづくりってどう関係があるんですか?



日本には四季があり、木工や漆器、陶磁器などは気候や素材の特性に合わせて発展してきました
職人たちは自然を「師匠」として技術を磨いてきたんですよ



しぜん、ししょう?



自然は大きな先生みたいなものなんです
たとえば、陶磁器を作る時は土や火と話しながら作ると言います



へえ、自然と話すって面白いですね!



話すというのは、自然を感じ取るという意味です
そうして作られた茶道具などは、自然素材の美しさを最大限に引き出しています



日本のものづくりと自然の関係って面白いですね



その他にも、自然はその瞬間やその個体にしかない不完全さがありますが、その不完全さをも受け入れます
また、「用の美」に見られる、日常生活という“人と物との自然なあり様”に美しさを見出す感性も大切にしています



柳宗悦が提唱した「用の美」は、日常生活で使われる実用的な道具や工芸品に宿る美の思想です。自然な素材とシンプルな形、そして長く愛用されるという日常の中での美意識を称賛しました。



日本的ものづくりには、自然と対話し共に生きる姿勢が現れているんです
現代、サステナビリティやエコデザインの観点から、日本の「自然との共生」の考え方が再評価されています



自然との共生?



「素材を活かす」「不完全さを受け入れる」「長く共にする」という事です



きょうせい、たいせつ!
現代においては、サステナビリティやエコデザインの観点から、日本的ものづくりの「自然との共生」思想が再評価されている。
この思想は、自然と対話し共に生きる姿勢、「素材を活かす」「不完全さを受け入れる」「長く共にする」という自然観に根ざしている。
この考え方は、単なる伝統文化にとどまらず、現代の製品デザインにも広く影響を与えている。たとえば、再生可能な素材の活用や、製品のライフサイクル全体を考慮した設計、廃棄物を最小限に抑えるミニマルデザインなどが挙げられる。また、環境に優しい製品開発を推進する企業は、この「自然との共生」思想を基盤として持続可能な社会の実現を目指している。
「もったいない」に宿る日本のエコデザイン思想
日本の物作りとは物とのつながりである、だから物が壊れたら終わりではない。もったいないの精神はここからも読み取れる。
たとえば、壊れた陶器を金継ぎで修復し、その修復跡を新たな美として受け入れる文化は、物に新しい命を吹き込む哲学である。また、着物の直線裁断による無駄のない布地活用や、世代を超えたリメイクは、物との長期的な関係性を大切にする姿勢を示している。
さらに、和紙や竹、木材といった自然素材の活用も、物との持続可能なつながりを築く工夫の一つである。
物を単なる消費対象ではなく、共生のパートナーとして捉える文化的背景を持っている。



エコデザインって知っていますか?



聞いたことはありますが…



エコデザインは、資源やエネルギーのムダを減らして、環境にやさしいものの作り方のことです。



日本の伝統的な文化にもエコデザインに通じる考え方があります。漆器や陶器を修理して長く使う文化、金継ぎという壊れた器を美しく直す技法とかです



それって、もったいない精神にもつながりますね



エコデザインは日本の「もったいない」文化と深く結びついています。「もったいない」は、資源や物を無駄にせず、大切に使う心を表しています。この精神は、エコデザインが追求する再利用、リサイクル、省エネルギーといった持続可能な工夫と調和します。



「もったいない」の心もエコデザインの大事なポイントなんです。自然素材を使ったり、四季に合わせたデザインもエコと言えますね



現代のサステナブルファッションも、着物文化から学ぶことが多いんですよね



着物はリサイクルやリメイクが簡単で、ゼロウェイストの考え方に近いんです
金継ぎも、壊れたものを新しい美しさとして再生するアップサイクルの先駆けとも言えますね



ゼロウェイストは、廃棄物を極限まで減らすことを目指すライフスタイルです。再利用、リサイクル、堆肥化、無駄の削減を通じて、環境への負荷を最小限に抑えることを重視します。持続可能な社会の実現に貢献する考え方です。



エコデザインって、実は昔から日本に根付いているんですね



自然と共生し、無駄を省き、修理や再生を美とする。その感性が、現代社会のエコデザインに生きているんです



エコデザイン、カッコいい!!
「Mottainai」はエコのキーワードとして世界でも注目されている。
現代のサステナブルデザインも、物とのつながりを再認識する動きの一環である。金継ぎの思想はアップサイクルの概念と親和性が高く、修理を超えて新たな価値を生み出すアプローチとして注目されている。着物は布を裁断せず直線的に縫うため、リサイクルやリメイクが容易であり、ゼロウェイストファッションと通じるものがある。
エコと「もったいない」は、私たちと物との深いつながりを再考させる重要な概念である。
エコは環境負荷を最小限に抑え、持続可能な社会の実現を目指す考え方であり、「もったいない」は物の本質的価値を尊重し、長く大切に使う日本特有の精神を示している。「無駄を削ぎ落とす美学」や「わび・さび」の価値観は、物への敬意を織り込んでいる。
両者は物への敬意と感謝の気持ちを基盤としており、単なる節約や再利用を超えた価値観を提供する。
海外に広がる「金継ぎ」と「もったいない」の思想
金継ぎは、単なる修復技法ではない。壊れた器を漆で継ぎ、金粉で仕上げるその過程は、物の「生まれ変わり」であり、「再生の儀式」だと言えるだろう。割れた跡が「欠陥」ではなく、「歴史」として息づいているのだ。
欧米のデザイン界では、「Repair as Design(修理をデザインとして捉える)」という概念が広まり、壊れた部分を隠すのではなく、あえて見せることで新しい価値を生み出す試みが増えている。これは、一見ネガティブに捉えられがちな「不完全さ」を肯定する姿勢であり、私たちが完璧さを追い求めがちな現代社会への静かな反論でもあるのだろう。
再生の美学は、ファッションやインテリア、アートの世界にも影響を与えている。破れた服を刺繍や異素材で補修し、新たなデザインとして再生させ、家具デザインでも、壊れた部分をあえて際立たせることで「味わい深さ」を生み出しているという。



「金継ぎ」と「もったいない精神」がどのように海外に影響を与えているかを見てみましょう



金継ぎって日本だけのものじゃないんですか?



現代ではは欧米でも金継ぎの考え方がデザインに取り入れられているんです



金継ぎは壊れた器を漆で継ぎ、金粉で仕上げる日本の修復技法。でも、海外では「Repair as Design」という考え方として、修理した部分を隠すのではなく、デザインの一部として見せる発想が流行っています。



どんなものに使われているんですか?



ヨーロッパでは靴や家具、家電などの修理部分をあえて目立たせるデザインが増えているそうです





なおして、もっとかっこいい!



「もったいない精神」も海外で知られているんですか?



「もったいない」という言葉は元々仏教から来ていて、「無駄にしない」「大切にする」という意味があるんです
2005年にはケニアの環境活動家ワンガリ・マータイさんが「MOTTAINAIキャンペーン」を広めて、世界中に知られるようになったんですよ



どんなふうに広まったんですか?



このキャンペーンでは「Reduce(削減)」「Reuse(再使用)」「Recycle(再資源化)」に「Respect(尊重)」を加えた“4R運動”として国連でも紹介されたんです
ヨーロッパでは「MOTTAINAI」という言葉自体が環境保護のキーワードとして定着しているんですよ



世界中で日本の考え方が役立っているんですね!



「もったいない精神」はサーキュラーエコノミー(循環型経済)の考え方にも深く関わっています
最近では、環境学や経済学でも日本の「もったいない精神」を事例として研究することが増えていますね



ボンド、もったいない…ゴミ、すてない! なおして、つかう!



金継ぎも「もったいない精神」も、ただ物を直すだけじゃなく、新しい価値を生み出すという、日本のものづくりの大切な考え方なんです
「もったいない」には、Reduce(ゴミ削減)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)という環境活動の3Rに、Respect(尊敬の念)が込められている。
2005年、ケニアの環境活動家ワンガリ・マータイさんが「MOTTAINAIキャンペーン」を国際的に提唱したことで、この言葉は世界中に広がった。
「MOTTAINAI」には単なるリサイクル活動を超えて、あらゆる存在への敬意が根底にある。それは、物だけでなく人や文化への敬意にもつながる深い思想であり、「過去を抱きしめ、未来へと繋ぐ」美しい行為なのだ。
結局のところ、金継ぎともったいない精神は、物だけでなく私たち自身にも教えてくれる。失敗や欠損を恥じるのではなく、それを受け入れて「自分だけの物語」として誇ること。そんな生き方が、心を豊かにしてくれる。
私たちの手元にある「壊れたもの」を見つめ直すとき、それは単なる過去の残骸ではなく、未来へと織りなす新たな美しさへの入り口なのかもしれない。
具体的な国内外の事例を紹介
「金継ぎ」や「もったいない」の精神をデザインやブランドに取り入れている海外の実例を、少しここで紹介してみたい。




– VESSEL – Limited Edition “KINTSUGI Collection” –
ゴルフバッグ(Player V Pro/アイテム用ヘッドカバー等) 縫い目やステッチ、ゴールド刺繍で「亀裂」「継ぎ目」の線をデザインとして強調。「割れた器を修復する」金継ぎの観念を、バッグという日用品に応用。


– Thompson – “Kintsugi Collection” –
キッチンシンク(fireclay apron-front sink)コレクション 割れ物を修復する本来の技法そのものではないが、「ひび・線」を金・銀・銅で象ったインレイ(装飾線)で金継ぎを彷彿とさせるデザイン。機能的なシンクにアートを融合。
– Kiriko × Madewell のコラボ –
米国のブランド Madewell が、Kiriko(日本の古布/ヴィンテージテキスタイルを再利用するブランド)と協力し、日本の “boro”(日本の古い布を継ぎ接ぎした布文化)や mottainai の考え方を衣服に反映。余り布や古布をアクセントとして使うなど、捨てられそうな素材をデザインに活かしている。








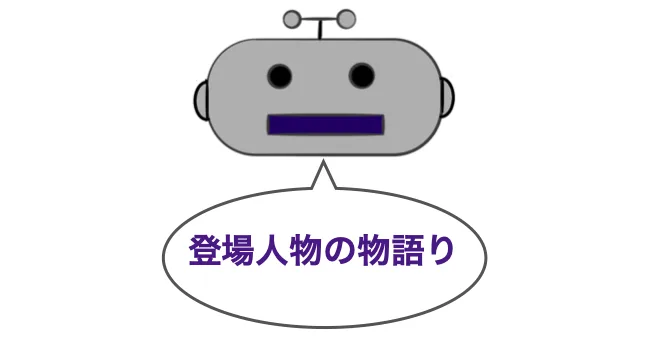







コメント