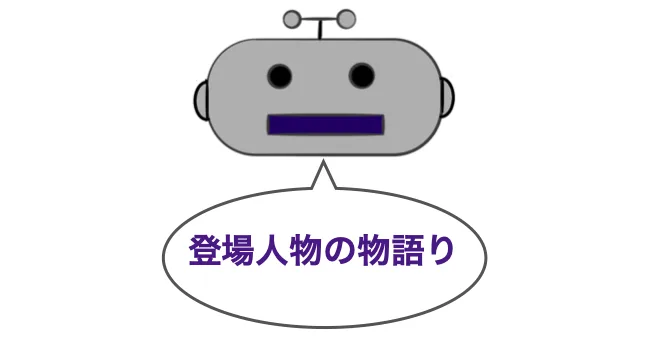2025年– date –
-


つながりの思考で実現するサステナブルな社会
コントロールの限界:気候変動と文明発展の関係性 地球の歴史において、この数千年は比較的穏やかで、変動の少ない時期であったという。その穏やかな環境の中で、人類は物事をコントロールし文明を作り上げた。 コントロールの本質は、物事を効率的かつ効... -


今この瞬間を愛でる:日本の四季と季節行事
「四季を愛でる心」―日本文化に根付く季節の楽しみ方 「日本には四季がある」と言うより、「四季を愛でる風習がある」。 過ぎ去る季節をただ眺めるのではなく、移ろい行く一瞬を丁寧に切り取る。それが四季を愛でる心だ。 「日本には四季がある」ってよく... -


日本文化におけるつながりと共存
日本の物作り×日本食:素材と人が紡ぐ共生の物語 日本食においては、食材の持つ本来の味や香り、食感を尊重することが重要である。過度な加工や味付けを避けることで、素材そのものの良さを引き出す。この姿勢は素材を「コントロール」するものではなく、... -


「合理性」だけじゃない!心でつながる「共存社会」の重要性と多様性の力
お金より大切なものって何?現代社会が求める“力”とは 情報は現代社会において強力なコントロールツールである。 デジタル社会では物質よりも情報の重要性が増し、人々は意識して情報を扱い、それに依存するようになった。 過去には、物質的な豊かさが幸福... -


多様性が未来を変える!つながりが生む新たな価値とは?
日本文化における借景の美学 海外の人々にとって、日本の文化は自然と人間が一体化し、共存する姿として映るという。 庭園の前景に庭を配置し、遠方の山野と重ね合わせることで景観を構築する手法が借景である。これは、雄大な自然を庭の一部として取り込... -


日本文化の多様性とつながり|ゆるキャラと空気を読む文化を探る
日本文化の多様性 日本は太古の昔から、大陸の多様な文明を独自の形で発展させてきた。 島国である日本は、限られた価値あるもののみが海を越えて伝わってきたため、辿り着いた文物は捨てられることなく受け容れられ、後に吟味された。その結果日本は漂流... -


混迷の時代を生きる
物質よりも心と情報!現代社会で求められる新たな豊かさとは 2021年の世論調査では、物質より心の豊かさを重視する人が半数を超えた、と報告されている。 欲する物が明確に存在していた頃は、貪欲に物質を求めればよかった、それで幸せだった。しかし... -


AI時代にこそリンクする情報と人の考え
テクノロジー×文化:AI時代の人間性とは? デジタル技術は、かつては単に情報を効率化する手段だったが、今や情報そのものを生産する技術へと進化している。 AIは高速かつ無休で膨大な情報を処理し、組み合わせ、新たな情報を生み出している。 この進化は... -


つながりを捉える思考
【生き抜く知恵】変化に強い日本文化|自然災害と共生する「つながり」戦略 日本では、地震や災害など自然の猛威に直面することで、変化は避けられないものとして捉え、対処法として個々の存在だけでなく、人と自然など物事同士の関係性、「つながり」を重... -


変化の文化日本
日本の再生文化 vs 西洋の永続文化|物への信頼とつながり 石の文化と木の文化についてのお話です ある旅番組を観ていた。 西洋を旅するその番組で、数百年の歳月を重ねた石組の遺跡を、そのまま住居として今も活用し続けている様子を紹介していた。 TVの...